大阪府大東市の阪奈自動車教習所に、自衛隊大阪地方協力本部の深草貴信本部長が訪問され意見交換をいたしました。オーナーの松本会長が私を自衛隊支援活動に引き入れてくれました。写真前列右から深草本部長、松本高会長、中西貞正社長、後列左、松本豊副社長。

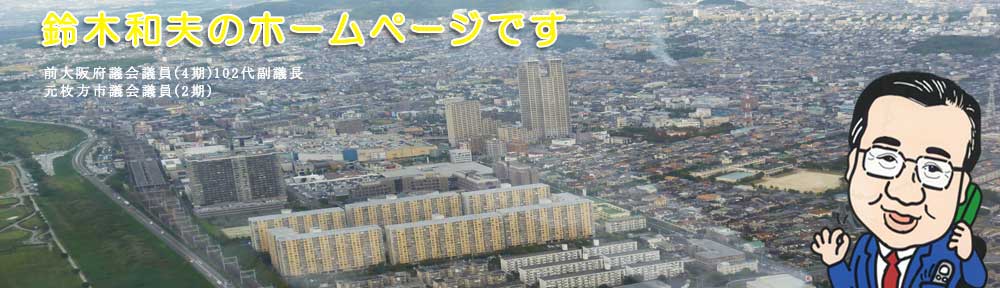
台湾訪問3日目の23日、台湾最南部の屏東県庁(ヘイトウ)を訪問し周春米・県知事、鄞鳳闌・傳播及国際事務処長、楊英雪・教育処長、鄭永裕・農業処長、倪國鈞・交通旅遊副處長らと会見。都市交流、高校間の提携、農産物の振興などが話題になりました。
屏東県は、台湾最南端の農業・漁業が盛んな地域。自然を残す熱帯性気候でパイナップル、バナナ、マンゴー等の果物畑が点在しています。屏東の東港は、マグロや桜エビの収穫が国内一の港町。国内初の国定公園の墾丁(カンディ)でも有名。
周知事は、1966年生まれ。国立台湾大学法学部卒後、台湾高雄・屏東地方裁判所裁判官、屏東弁護士会理事長を経て立法院立法委員(国会議員)に、2022年12月から屏東県知事。





台湾訪問の第2日目10月22日は、台湾有事で注目されている金門県政府(金門島)の李文良・副知事、董雲馨・観光副局長を表敬訪問。
金門島は、台北から約270㎞、中国アモイからは約5㎞しか離れおらず、国共内戦時は最前線の軍事拠点で1958年8月23日から44日間に中国軍が約47万5000発の砲弾を撃ち込み79年1月までの21年間戦闘状態が続いていました。
2001年に両岸の往来の制限が緩和され、19年には中国から約40万人の観光客が訪問しましたが、コロナ禍の影響や台湾有事での緊張状態のなか今年は1万人程度に激減しています。厳しい経済状況でインフラ整備に取り組まれています。特に教育の充実に力を入れられ大阪との学校間交流の要望を受けました。




