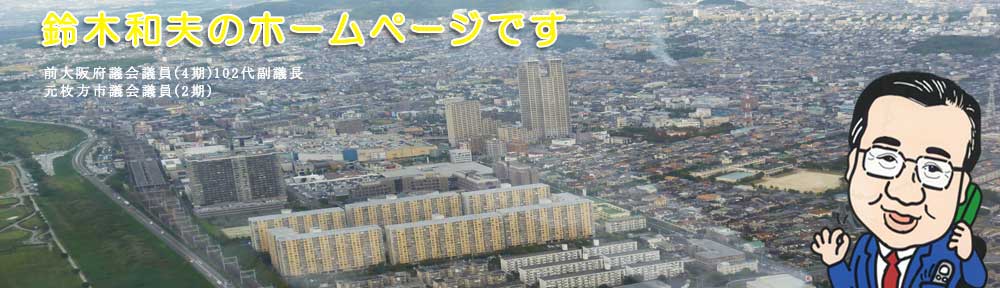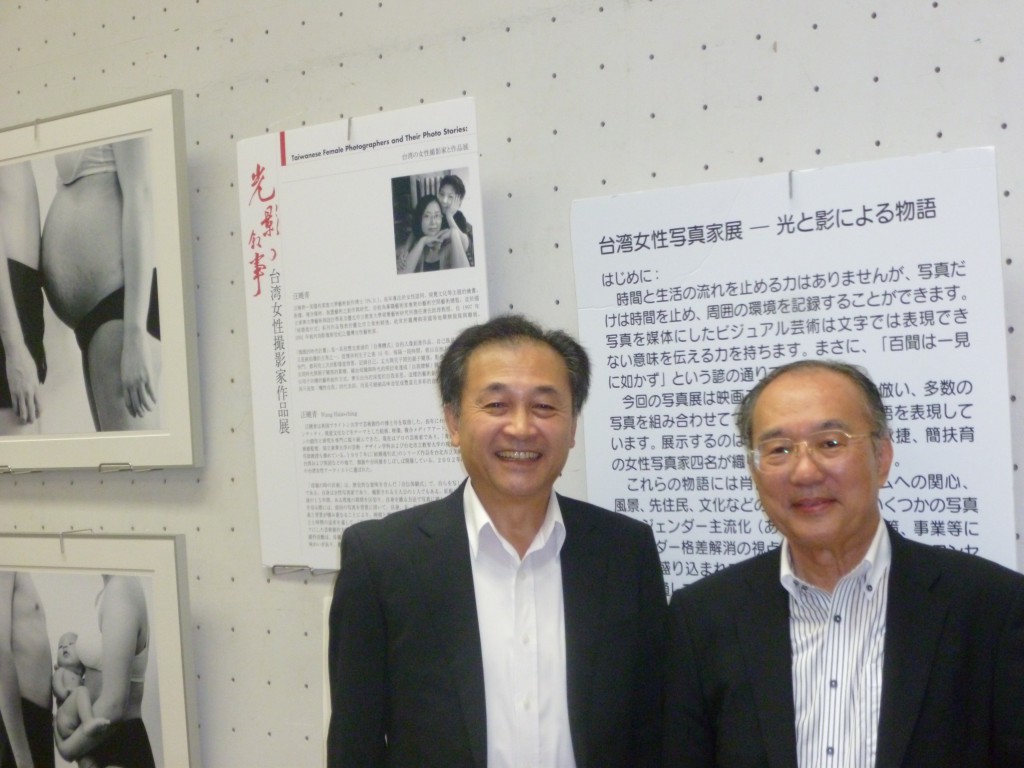10月6日、中華民国留日大阪中華総会(洪勝信会長)主催の祝賀会に招かれ出席しました。スイスホテル南海大阪で、台湾・日本の約800名が国慶節をお祝いし、日台の絆を深めました。
「 」カテゴリーアーカイブ
第22回阪奈フェスタ
激戦の交野市議選
現存天守の国宝5城を制覇
現存天守が国宝に指定されている城は、姫路城、彦根城、犬山城、松本城、松江城の5城です。超党派の大阪府議OBで構成する大手会で、9月2日、犬山城を視察する機会がありましたので訪れました。これで「国宝5城」を~制覇~しました。残るは、現存天守の重文7城(弘前城、丸岡城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城、高知城)のうち、弘前城、備中松山城、宇和島城が未制覇で機会があれば挑戦したいと思っています。
また、行程で、豪華貸切バスのジパングのカリスマガイドの中田さん(右)と女性ドライバーの畑田さん(左)と知り合いました。お二人とも、無理難題も笑顔で対応するプロフェッショナルです。問合せは、ZIPANG株式会社(本社・門真市)電話072-887-2100
大阪土地家屋調査士会との研修会
大阪土地家屋調査士会(加藤幸男会長)、同政治連盟(利川良一会長)は、今春の統一地方選挙で推薦を受けた公明党の大阪府議・市議で構成する顧問団と、表示登記制度、公共建築物の未登記問題、空家対策等をテーマに研修会を9月1日に行いました。席上、これまでの顧問団に加え、垣見大志朗(府議)・内海久子(同)・肥後洋一朗(同)。八尾進(大阪市議)・山田正和(同)の5氏が本日、顧問に就任しました。現顧問は、三宅史明・林啓二・三浦寿子(以上府議)。小笹正博・高山仁・明石直樹(以上市議)。鈴木和夫(元府議)。